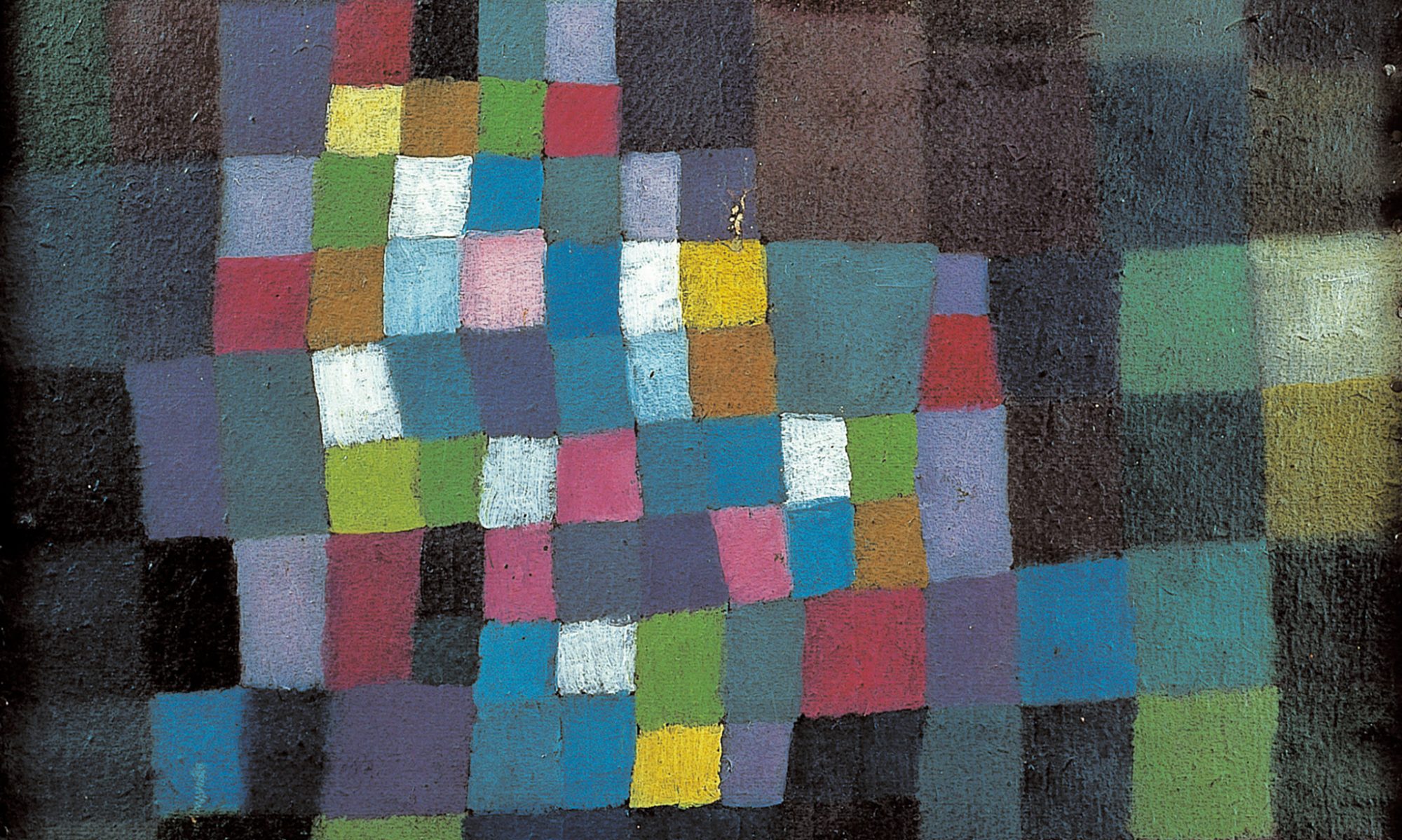「人生ほど、生きる疲れを癒してくれるものは、ない。」
思わず「うーん」と考え込まずにはいられないこの言葉。私はこの言葉をどこかで知り、そして誰の言葉かわからないままに、かつて同僚の送別会での送る言葉として紹介したこともあった。昨年、ふと本屋で本をパラパラめくっていると、いきなりこの言葉が入ってくるじゃないか。「ミラノ」という題のウンベルト・サバの詩、冒頭の言葉はその最後の二行としてあった。訳者は須賀敦子、とある。
こうして私は、この詩を扉に掲げてあるこの本を読むことになったのだが、一読、これは自分のために書かれた本ではないかと思い、続けて彼女の生前に出版された5冊の本を読み、そしてやがては文庫本の須賀敦子全集などをひっくり返すようになったのである。
コルシア・デイ・セルヴィ書店。もとはと言えば、第二次世界大戦末期、ドイツ軍に占領されたミラノで、知識人による対独レジスタンスが母体となって生まれた書店。戦後は、「あたらしい神学」のもと、熱病のように有機的な共同体としての生き方を追求しようとしたカトリック左派の試みの場所。
著者は、日本にいる時からこの書店につよく惹かれ、イタリア留学が決まった時、この書店の人に会うことを大きな目標にした。そして、留学後、すぐにかかわりを持ちはじめ、やがては、書店の中心人物の一人であるペッピーノと結婚、夫婦で書店の活動に参加していくことになる。しかし、数年後ペッピーノは病気で亡くなり、やがて彼女は1971年に日本へ帰国する。
このように、著者にとっては実質的に10年あまりの関わりであった「コルシア書店」だが、この本では、その中心人物であったあの人この人について、あるいは、激しく移り変わる時代の流れの中で変貌していく書店の運命のいくつかのエピソードが、時を経た落ち着きのある筆致で語られる。しかし、著者がこれらを書いたのは、日本に帰国してすぐのことではない。それから実に20年も経った、著者が60歳を過ぎてからのことだ。この本で注目すべきは、たしかにその「時間」というものかもしれない。
この本の中で著者は、ナタリア・ギンズブルグの自伝的な小説についての感想を、登場人物の1人から「きみは、どう思う?」と聞かれて答える箇所がある。「自分の言葉を、文体として練り上げたことが、すごいんじゃないかしら。私はいった。それは、この作品のテーマについてもいえると思う。いわば無名の家族のひとりひとりが、小説ぶらないままで、虚構化されている」と。この評は、まったくそのまま、この本の内容にもあてはまることだ。
また、著者は別の場所で、ある若者の小説について、こうも語っている。「十分な客観化に到らないで、作者の個人的な嘆きが、シチリアの泣き女の葬送唄のように重苦しくたゆたって、作品の印象を弱めていた。」
おそらく、20年という「時」を経ずしてこの本が書かれていたならば、それは、あくまでも「須賀敦子のイタリア体験記」ではあっても、その本を読んだ人間が「これはまるで自分のことが書かれてある」という感想にまでには到らなかったのではないか。
「コルシア・デイ・セルヴィ書店をめぐって、私たちは、ともするとそれを自分たちが求めている世界そのものであるかのように、あれこれと理想を思い描いた。(中略)それぞれの心のなかにある書店が微妙に違っているのを、若い私たちは無視して、いちずに前進しようとした。その相違が、人間のだれもが、究極においては生きなければならない孤独と隣りあわせで、人それぞれ自分自身の孤独を確立しないかぎり、人生は始まらないということを、すくなくとも私は、ながいこと理解できないでいた。若い日に思い描いたコルシア・デイ・セルヴィ書店を徐々に失うことによって、私たちはすこしずつ、孤独が、かつて私たちを恐れさせたような荒野でないことを知ったように思う。」
この「あとがきにかえて」の最後の部分を、私は何回読み返しただろうか。ここには「時間」という濾過装置によって、したたり落ちてきたものだけを拾い集めた結晶のような文体がある。