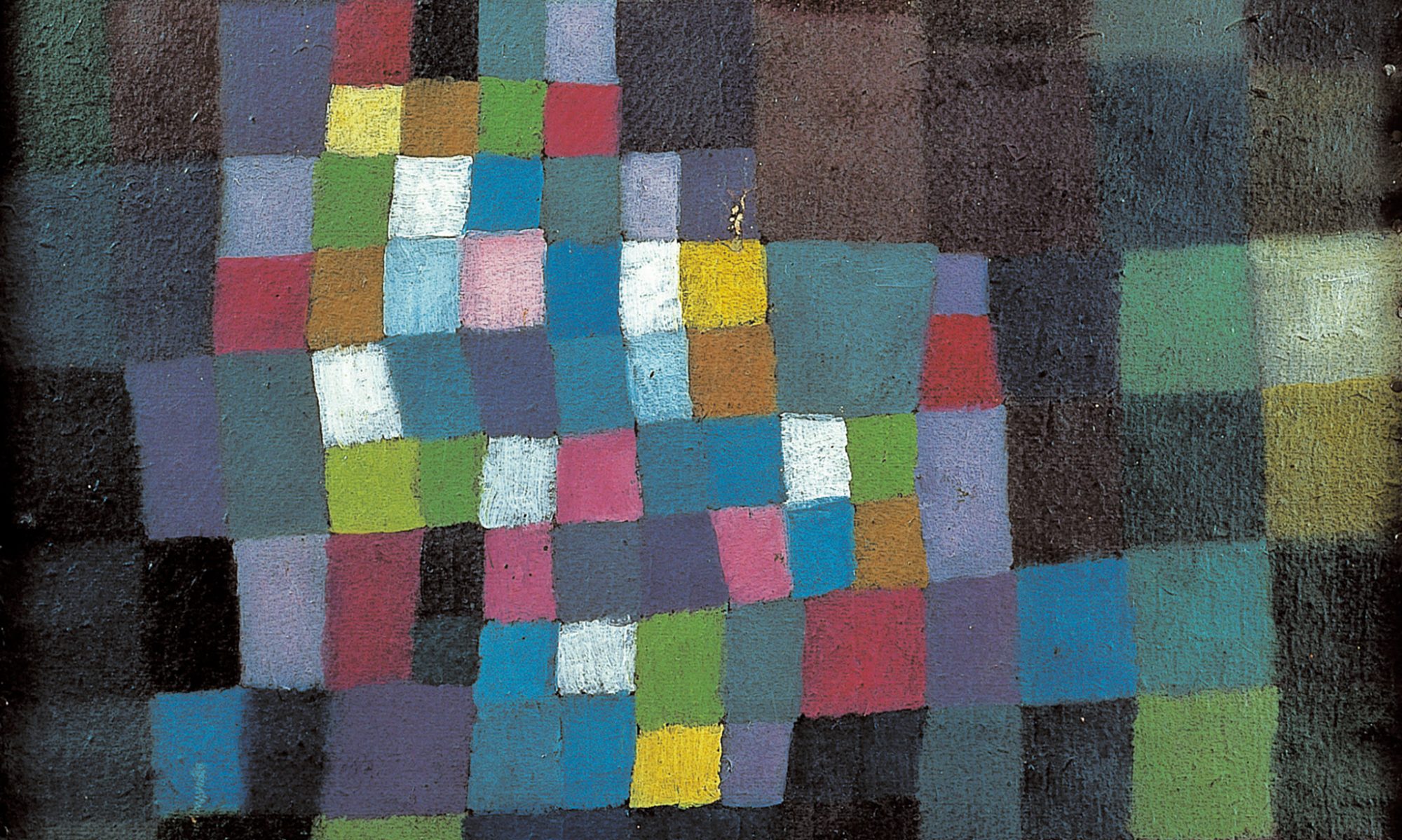「おお、なつかしいなあ」と思った。何が? この本の中の時代の空気感が。
もちろん、まずは村松友視という名前自体の懐かしさでこの古本を買ったのだが、この中で著者と交流しているたとえば、赤瀬川原平、糸井重里、南伸坊、篠原勝之などといった名前は、私にとっては、自分が学生時代を過ごした東京の70年代の終わりから80年代前半にかけての空気そのもののような名前である。アブサンというネコと村松夫妻との20年に及ぶつきあいの日々が綴られたこの本のBGMには、その当時の空気感がしっかりと流れている。
この本はネコ好きにとってはたまらない1冊なのかもしれないが、そこまでではない私のようなものからすれば、この本の魅力というのは、アブサンに対する著者のつきあい方の迷いといった繊細な部分なのである。たとえば、多くの人が「あらあら、いけまちぇんねえ」などと、ネコを子どものように扱う言葉遣いをすることに著者は抵抗を感じてしまう。それは、人間の子どもに失礼なのではなく、アブサンに失礼じゃないか。あくまでアブサンは尊敬すべき伴侶であって、子どもの代用品なんかじゃない、と。だから、著者は、本当の友人に対するように「これはまあ話さなくてもいいことなんだけれど、しかし話さなければ伝わらないわけで……」などと「対等」に話しかけたりなんぞするのであるが、そのとたんアブサンは迷惑そうに、どこかに行ってしまう。いったいどういう対し方をすればいいのか、悩んでしまうのである。私にはそんな場面がなんともいえず面白い。
また著者は、自意識過剰でヘリクツ屋でもある。
「あのね、ネコっていうのは表情のあらわし方が屈折していてね、その場の様子だけじゃ判らないんだよ」(中略)「そっちの方が屈折しているんじゃない?」「俺が屈折しているんじゃないよ」「そうかな……」「屈折しているのが俺なんだ」「また始まった」カミさんは、あきれ顔で溜息をついた。
その自意識過剰は、ときにヘタレの捨て身の芸にもなる。
「こういうとき、カンニング気分でひそかに辞書を引くのが私の習慣になっている。辞書を引いて事が明らかになると、まるでそのことを十年も前から知っていたように喋り出す……これがもう私の性(さが)といってよいほど定着しているのだ。まったく、いろんなことをごまかして世間様への体裁をつくりまくり、己れの正体がバレないよう、日夜おずおずと上目遣いで作家をやっているワタクシでございます。」
アブサンは著者夫妻の家で21年間をともに過ごした後、1995年2月10日に亡くなる。そして、この『アブサン物語』の単行本が出るのが、その年の12月のことである。ところで、その1年というのは、いったいどういう年だったか。1月17日には、阪神淡路大震災が起こり、まだ、その余燼冷めやらずといった3月に、こんどはオウム真理教による地下鉄サリン事件が引き起こされたのである。連日のテレビ報道の陰惨さで、時代の空気は、この本の基調となる80年代の空気といったものから、一気に険しいものへと変わっていった年だった。今から思えば、著者がこの原稿を書いている間は、多くの人が、自分たちの社会が足元からひっくり返っていくような危機感や恐怖感を持った、その始まりの年だったのだが、そういう出来事がいっさい出てこないのである。これは、あきらかに著者の強い意思とみるべきだろう。
「アブサンの死の翌日、カミさんの目は腫れ上り、三日間というものもとに戻らなかった。私はカミさんに‘‘辰吉丈一郎の十二ラウンド目”という綽名をつけた。私たちは、庭を掘ってアブサンを埋め、カミさんが故郷の河原から拾って大事にして持っていたという握り拳くらいの小石を、墓石に見立てて上に置いた。」
世の喧騒をよそに、ひたすら「人生の重大な伴侶」だったアブサンとの時間を辿りなおした静かな本になった。
Cat’s MeoW BookSさんを訪れて本書を買ったことの記念に。