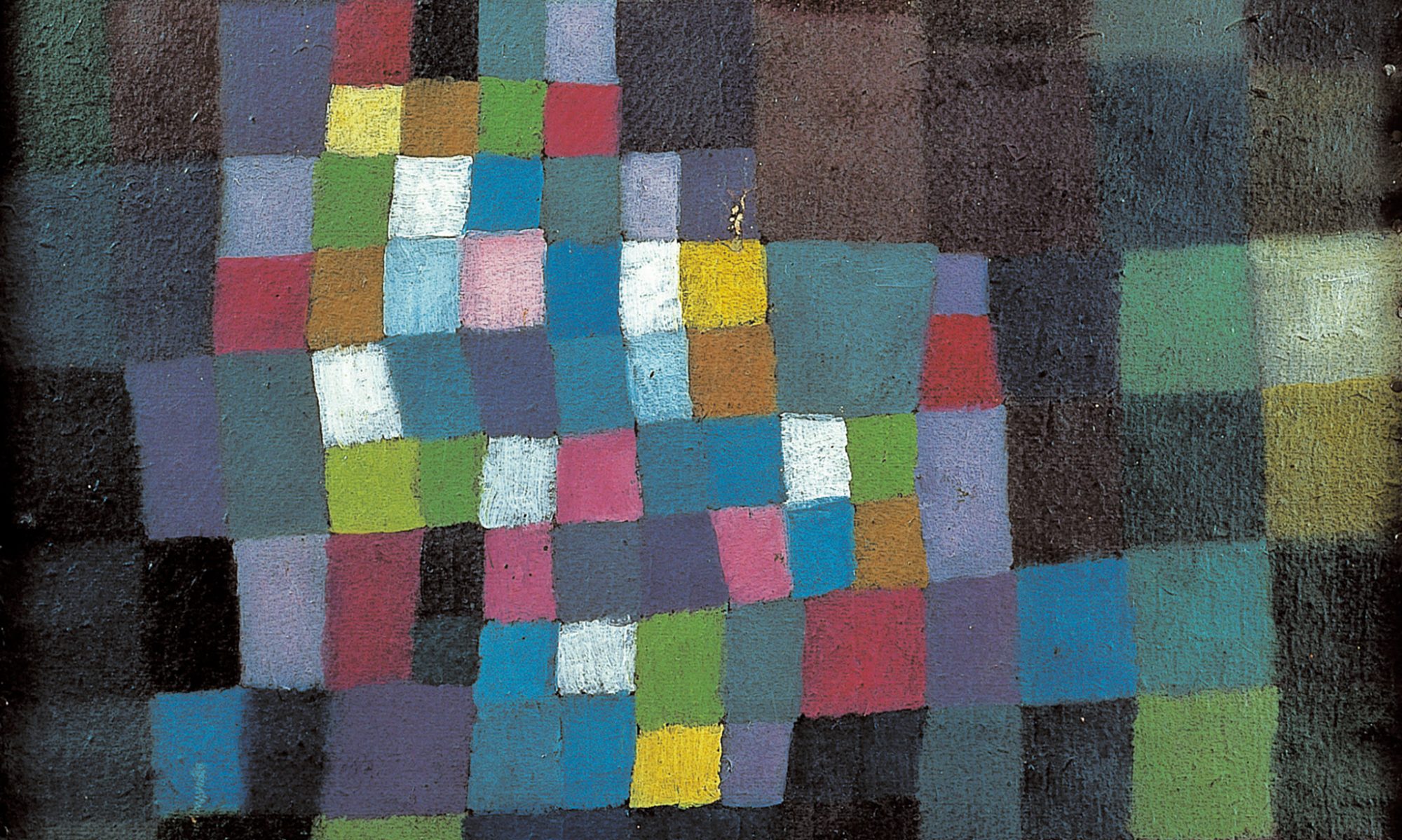この本の著者徳永進さんは鳥取県のお医者さん。長らく地域の病院に勤務していたが15年前、鳥取市内にホスピスケア(終末医療)を行う「野の花診療所」を開設した。そこで見送った人(つまり亡くなるまで世話をした人)は1000人を超えるらしい。
彼は、医療現場もまた「正解」や「正義」が固定されやすい世界だという。マニュアル言葉、告知、余命、副作用、生存率などなど。それらがスプリンクラーのように上から下に一方向の情報として患者さんに降りそそぐ。
そういう医療の息苦しさの中で、徳永さんは対立するように思える「反対言葉」に着目する。「〈生きる〉と〈死ぬ〉」「〈はい〉と〈いいえ〉」「〈泣く〉と〈笑う〉」などなど。せめて、その + と - の二極の振りはばの中から思いもかけず「湧いてくる言葉」を大切にしていきたいというのが彼の考えだ。そのようなできごとを折りにふれて書きつづったのがこの本である。
たとえば「伝える」(他動詞)ことと「伝わる」(自動詞)ことをめぐっての話。ある時、がんの女性の患者さんから「がんでないならがんでないと、はっきり言って」と詰め寄られた。彼は「ええ、がんじゃありません」ととっさに嘘をつく。「ああよかった。その一言が聞きたかった。」しかし女性は、そのあと家族を呼び、葬式のことやお墓のことを話していた。伝えなかったのに伝わったのだ。
「〈素手〉と〈手袋〉」の項では、認知症の母を家で看取った60才の男性の経験談もある。入浴の介護がむずかしく母も不安顔だったのだが、あることをしたら入浴がとてもスムーズになり、母も安心するようになったという。それは「ぼくも裸になって入ったんです。素っ裸で。」ということだった……。
「泣く」はずの死の中にも、しかし「笑い」がある。死んだと思って「よくがんばったよ」と家族が泣き出した直後、患者さんがまた息を吹き返す。「あっ、ごめんごめん」と、見守るみんなが目に涙を浮かべ、笑う。つまり「反対言葉」とは対立でなく解け合う世界なのだ。
こういう話、もっと学校でもなされなきゃと思うんだけどね。それこそ「正義」が固定されやすい本家の学校なんだから。(岩波書店 本体1700円)