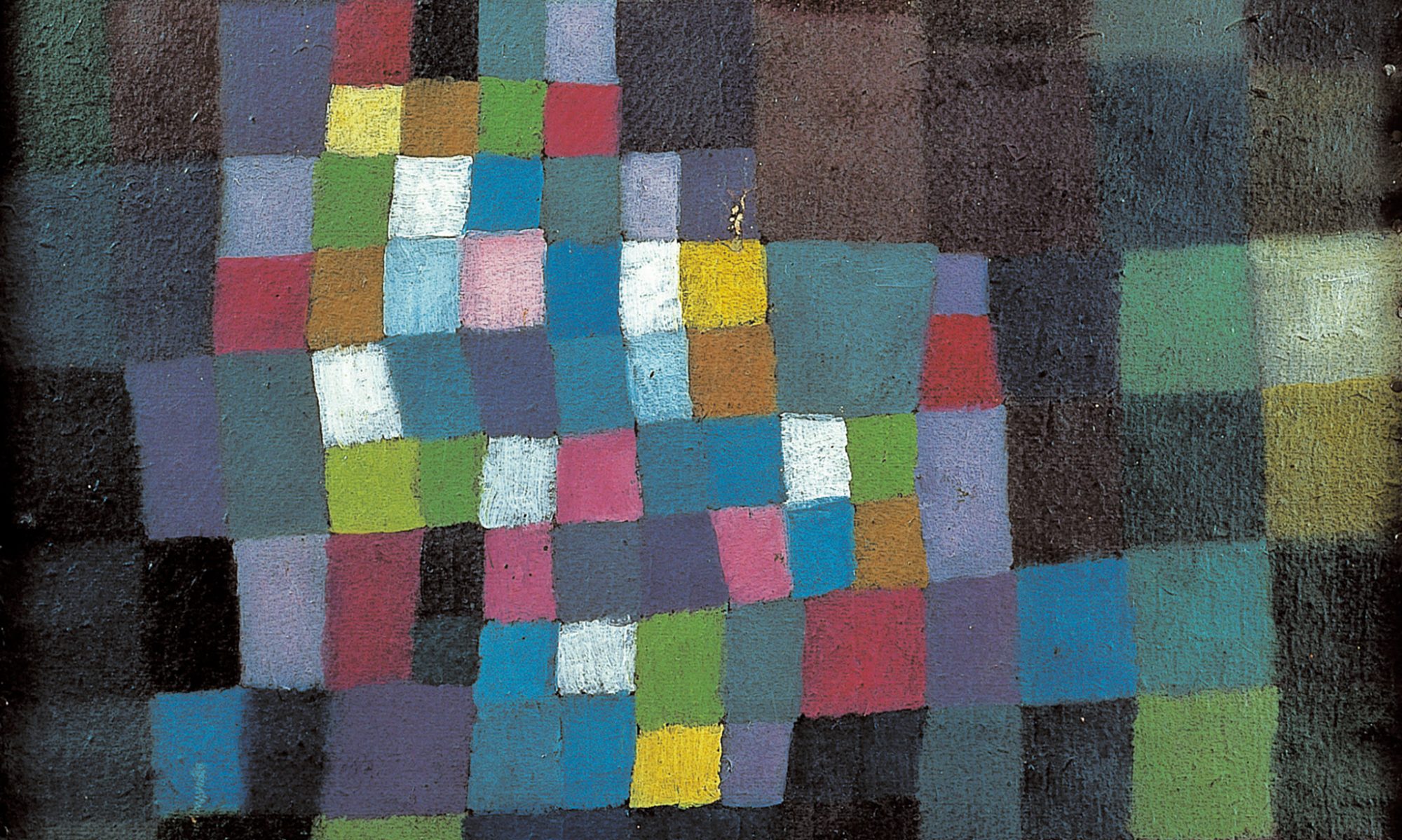「その1」でも書いたように、徳永進さんは鳥取県の「野の花診療所」という小さなホスピスのお医者さんだ。若いころからずっと本を書き続けてきたので、もう十数冊にもなるはず。ふつう、それぐらい書き続けていると、誰でも同じことの繰り返しにもなったりするのだが、今年の6月に出た新刊『「いのち」の現場でとまどう』を読み、くり返しどころか、現場に徹することからくる融通無碍のユーモアといったものや、ある種の凄味さえ感じさせる中身になっている。
たとえば「がんは告げるべきか、隠すべきか、どちらが正しいか」という問いがある。私たちの常識としては、この問題はかつては医療の中での大問題であり、しかも結論はわかりきっていて、医療者側も家族も、それを患者本人にいかに隠すかということに、多大なエネルギーを注いできたはずである。それが、いつの頃からか、インフォームドコンセントの流れなどもあり、今は「正しいかどうか」などとは関係のないところで、なしくずし的に本人に告げることがほぼ当たり前のことになっているのではないか。
しかし、徳永さんはこう言うのだ。
「問いそれ自体が間違っていることに気がつきました。」と。
「問いに振り回されて、正しい答えがあるのは当然であるかのように、〇だ×だ△だと答えを探そうとするのは、学ぶ者の『劣化』『質の低下』という事態です。」
「誰も『告げる』も『伝える』もしていないのに、いつのまにか『伝わる』。がんの告知というのは、コミュニケーションのなかでも特殊なケースですが、そこにも一般のコミュニケーションと同じように、『自ずからなる』自動詞の豊かな世界があるということを知りました。」
また、「安楽死」をめぐるやりとりも重要だ。「野の花診療所」はホスピス、つまり多くの人が亡くなって行く場所である。そこの医者である徳永さんは、「安楽死」をめぐって対立する二つの考え方をどう見ているか。まずは、安楽死反対の立場の意見について。
「医療者は安楽死を許してはならないという定義に出会った。『どんな場合であっても、死がその体全体をおおわない限りは医療者は患者を生かすという至上命令の中で、できる最大限のことをその患者にすべきだ』これがその定義だった。しかしぼくは、この定義の正しさを正しすぎると思った。確かにそれは正しい。しかし、解決が不可能な事情が複雑にいりくんでいて、現場でそれを貫くことは難しい。」
では、こんどは安楽死や尊厳死を積極的に認めるアメリカの医師ケヴォーキアンの意見に対しては?
「本人の意思、家族の意思、看護師や医師の意思が一致していれば、何も問題ないではないか、という議論もありうると思います。しかし、私が思ったいちばん大きな問題は、ケヴォーキアンのなかに『とまどい』がないということでした。人が生きるか死ぬかというときに、『これはどうしよう』、『いまはやめようか』といった『とまどい』があってはじめて、物事は運んでいきます。『とまどい』を欠いて『正義』の理念だけでやると、とんでもないことになりかねません。……臨床の現場では、『正義』を振りかざすような人ははた迷惑です。『正義』は怖いものです。『正義』によらずに、その時々にみんなで判断をつくっていくしかありません。」
このように、どちらの立場にもある「正しさ」そのものを疑っているのである。じゃあ徳永さんはどっちつかずの安全なところにいる人なのか?そうではない。
「ですから、医師は自分が無罪になることを望んではいけません。万が一には有罪になることをも覚悟したうえで、どうやって『正義』を貫くかではなく、どうやって人々を納得させる方法をつくっていくか、が問われています。」
どこかで誰かが、徳永さんのことを「角のない豆腐くらい柔らかい人」と評していたが、ここにある彼の「覚悟」はすでに凄味さえおびているように思う。
この本の後半は、大学の先生である高草木光一さんとの往復書簡という体裁でさまざまな問答が続いているが、その中には、徳永さんが学生時代から関わりをもってきたハンセン病についての時間の蓄積を感じさせる書簡もあり、一読の価値があると思う。